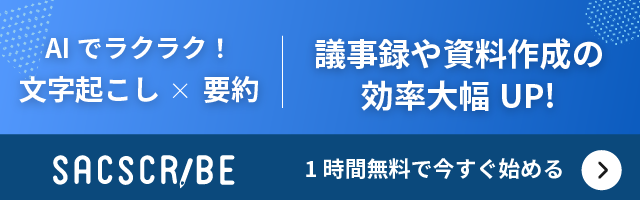在宅副業で人気の文字起こし。専門知識がなくても始められ、スキルアップすることで時間単価を上げられる点も魅力です。
パソコンやスマホで使える便利な文字起こしツールも多数あり、それらを活用することで文字起こしをさらに早く、簡単にできます。
テープ起こしは在宅副業で人気!仕事内容とおすすめのツールを紹介!
しかし、文字起こしを本業にしている人の中には、PCと再生機器のみ使い、再生スピードを調節しながら、ひたすらタイピング技術によって効率を上げている人も少なくありません。
便利なツールは数あれど、やはり基本となるのは音声を耳で聞き、それを正確にタイプする技術が重要ということです。
この記事では、文字起こしの基本といえるそれらの技術をさらに効率化、高速化する7つのコツを紹介します。
文字起こしを高速化する厳選7つのコツ
ツールを使わず文字起こしを高速化する6つのコツは以下の通りです。
- 文字起こしを始める前にまず内容を聴く
- ヘッドホンやイヤホンを使用
- 再生速度を調整する
- タイピング速度を上げる
- わかりにくい箇所はタイムコードを記載
- 頻出の単語は辞書に登録
- 専門用語を下調べしておく
それぞれ細かく見ていきましょう。
文字起こしを始める前にまず通しで内容を聴く
文字起こし初心者はすぐにも作業を始めたくなるものですが、まずは落ち着いてコーヒーでも飲みながら、文字起こしする音源を一通り聴いてみることをおすすめします。全体像を把握することで、その後の作業がやりやすくなります。
たとえば会議の音声の場合、全体の流れを知っておくと、ひとつひとつの発言の意味を理解しやすくなります。特にケバ取りや整文を行う場合には、どの発言が重要であるか判別できるようになります。
急がば回れで、初めに一歩下がって全体を見る、最初のコツとしてぜひ覚えておきましょう。
ヘッドホンやイヤホンを使用
文字起こしで音声を聴き逃さないために、ヘッドホンかイヤホンの使用をおすすめします。スピーカーの音は周囲に拡散して聴き取りにくいことがあるからです。
周囲の雑音をシャットアウトすることで、音声や作業に集中しやすい点もメリットです。
長時間作業をするのであれば、湿気や圧迫感のあるヘッドホンよりイヤホンの方がよいでしょう。ノイズキャンセラ機能があり、またワイヤレスであればコードが気になることもありません。再生機器とイヤホンにはできるだけ投資をしましょう。
再生速度を調整する
次に大事なコツが、再生速度の調整です。自分が最も聴き取りやすく、かつタイピングを進めやすい速度に調整します。耳で聞き取る能力とタイピング速度を考慮すると、高速タイピングが可能な人でも、普通よりやや遅めの速度で再生している人が多いです。
それにより、一時停止や巻き戻しの回数を極力少なくすることを目指します。いくら早く走っても、途中で立ち止まったり後戻りしているとゴールまでの時間は多くかかります。ペースを崩さず、一定の速度で安定して走り続けられるよう工夫をしましょう。
タイピング速度を上げる
文字起こしで時間単価を上げるコツは、タイピングの速度を上げる、これに尽きるといっても過言ではありません。タッチタイピングのスピードと正確性を高めることは、文字起こしに限らず、今後生きていく上できっと何かの役に立つでしょう。
まずは速さより正確性。正確性をきわめた上で徐々に速さを求める。日々の積み重ねが重要です。
わかりにくい箇所はタイムコードを記載
音声が不鮮明または理解できない言葉が出てきたときに、「○○(30分20秒)」と言葉と時間を記載しておくようにしましょう。長時間の音源を聴いていると、聴き取れない箇所は必ず出てきます。がんばって聴き取ろうと時間を浪費するよりも、わからないものはわからないと割り切って先に進みましょう。
文字起こしが一通り終わった時点でもう一度その部分を聴き直してみると、今度ははっきり聴き取れた、なんてことがあるのも文字起こしの面白いところです。
頻出の単語は辞書に登録
会議やインタビューでは、内容によって頻出の単語があるため、事前に辞書に登録しておくと効率的です。医療分野であれば検査や治療、薬剤、法律であれば法律名や法律用語など様々なものがあります。
パソコンの文字変換ですぐに表示されないものもありますから、事前に辞書登録しておきましょう。そうすることで、正しい単語を毎回探す手間が省略でき、文字起こしの時間短縮に繋がります。
専門用語を調べておく
文字起こしを効率化するには、その分野の専門知識や用語をある程度知っておくと便利です。最初に全体を通して聞く際、わからない言葉が出てきたらメモをしておいて、文字起こしにかかる前にさっと調べるだけでもかなり違いますし、その方法なら余計な言葉を知ることもなく過不足がなくなります。
まとめ:時間がない方にはSACSCRIBE
今回は、特別なツールを使わず、再生機器とPCを使って文字起こしをする上で、作業効率を高め、高速化を実現し、結果として時間単価を上げるコツを7つ紹介しました。
文字起こしに時間をかけられない場合は、自動文字起こしツールをつかって素起こしの時間を短縮しましょう。
クラウド型の自動文字起こしツールSACSCRIBEは、デバイスを問わず利用でき、アップした音源が自動で文字起こしされ、編集や校正も同一画面で行えるため作業時間の短縮が可能です。使いやすいUIで直感的に操作できる点も魅力です。
多数の音声、動画ファイルに対応しているため、面倒な動画の文字起こしも簡単にできてしまいます。
文字起こしに時間が取れない方は、ぜひSACSCRIBEのご利用を検討してみてください。